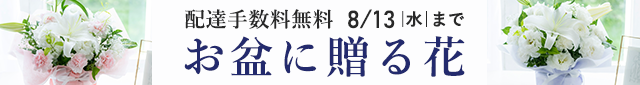
神棚の榊はいつ交換する?長持ちさせるポイントは?
日本人にとって馴染み深い宗教といえば、仏教のほかに神道が挙げられます。ですが中には、「榊を交換する時期や方法がわからない」という人もいるのではないでしょうか。そんな人のために、ここでは榊の交換時期や方法についてご紹介します。
神道や神棚について知ろう


榊の交換について学ぶ前に、神道について軽く復習してみましょう。
神道とは
神道は、もともと自然崇拝から始まった日本古来の宗教です。神道では、万物には神様が宿ると考えられてきました。山や岩などの自然物や、雷や地震などの自然現象、亡くなった人も神様として扱うこともあります。
そんな神道の神様の数は、信仰の対象によって増減するため、定かではありません。「数え切れないほどたくさん」という意味で「八百万の神々」と呼ばれます。最高神とされる天照大神といった神様をはじめ、実に多くの神様がいるようです。
神棚とは
神棚は、八百万の神様をお祀りする場所のことです。神社を模して作った宮形(お宮)と、棚板の両方を指します。
神社の本殿とそう変わらない役割を持っているため、目線よりも高い位置に置く、人通りが多い場所や不浄な場所は避けるといった細かな設置のルールがあります。
宮形の中には、伊勢神宮や氏神神社といった神社から戴いた御札を納めており、神様に感謝を捧げるとともに、祈願成就や家内安全など、さまざまなことを願うことができます。神饌としてお米や水、塩などをお供えし、両脇の榊立てには榊を活けるのが一般的です。
榊とは
榊は、神社もない時代から活躍していた植物です。大岩や大木など、神が宿りやすいと考えられる場所の周囲には、年を通して鮮やかな緑色を誇る、榊のような常緑樹が必ず植えられていました。そうすることで、神聖な場所であることを、人々に知らせていたといいます。
榊は、木ヘンに神と書くことからもわかるように、神様と密接な関係があると考えられてきた植物です。尖っているものには神が宿りやすいという考えもあり、尖った葉を持つ榊は、神事にも用いられます。神様をお祀りする神棚にも欠かせない植物といえるでしょう。
榊の交換時期や交換方法とは


◆榊の交換時期とは
毎月1日と15日に行なうのが一般的
榊の交換は、毎月1日と15日に行なうのが一般的です。このように時期が決まっているのは、神社で行なわれる月次祭(つきなみさい)が由来です。
神社では年間を通してさまざまな神事を行ないますが、神社によって、内容にも時期にもばらつきがあります。その中で、ほとんどの神社が共通して毎月行なう祭祀が月次祭です。
月次祭では神様への感謝を捧げ、国民の安泰や国家の繁栄などを願います。この月次祭が行なわれる日付が、多くは毎月1日や15日なので、神棚にお祀りした神様によって左右されることがありません。そのため、月次祭の1日や15日に合わせて榊の交換をするのが、一般的になったといわれています。
榊の元気がなくなってきたら
毎月1日と15日に交換するのが一般的ですが、榊の状態を見て交換するかどうか決めることも多いです。榊は、管理がしっかりできていれば1ヶ月近く持つことは珍しくありません。そのため榊が元気なら、交換時期を過ぎても交換しないこともあるようです。
ですが管理が悪ければ、1日や15日を待たずに榊の元気がなくなり、葉が落ちてきてしまうこともあるでしょう。そのようなときには、早めに交換する必要があります。
榊の交換時期は、明確に決められているわけではありませんので、榊の状態を見ながら交換しても構いません。
榊を長持ちさせるには
榊を長持ちさせたいと思ったのであれば、特に気をつけたいのが雑菌です。
まず榊立ての水は、毎日交換する必要があります。新鮮な水であれば、雑菌も繁殖しにくく、長持ちさせることができるでしょう。
また、榊立てや榊の茎をこまめに洗うことも有効です。銅(10円玉)を榊立てに入れたり、1滴だけ漂白剤を混ぜたりすることでも、殺菌効果が狙えます。
榊の茎を切るときに、根に近い部分で斜め45度に切るといった方法も、水の吸い上げがスムーズになるので、持ちを良くすることが可能です。
◆榊の交換方法とは
まずは榊の種類と本数を確認
まずは榊を購入しましょう。現在、榊はどこでも手に入りやすくなっています。ただ、榊には本榊とヒサカキがあり、地域によってはヒサカキを使うことがあります。どちらを使うのかは、購入前に確認しておくと良いでしょう。
また、本数は通常なら1本ですが、地域によって2本以上使う場合があります。左右で何本使うのか、交換前に数えるか、周囲に確認しておいてください。
榊立てに新鮮な水と一緒に
榊が用意できたら、榊立てから古い榊を取り、中の水を捨てます。
その後、軽く榊立てを洗ったら、新鮮な水を入れて榊を活けて神棚に戻しましょう。
交換時の作法は特にありませんが、神棚の飾り方にはルールがあり、榊の配置場所も決められています。必ず神棚の左右に置くようにしてください。
お米や水、塩といった神饌もこのときに交換し、神棚の周辺の埃を軽く払っておくと良いでしょう。
榊の処分方法は?
榊も神様にお供えしているものの一つなので、処分方法がある程度決められています。
神社でお焚き上げしてもらう方法や、海や川に流して自然に還す方法が正式とされています。ですが神社によって榊を処分してくれないところがあり、海や川に流すのも、あまり現実的な処分方法とはいえません。
現在では、交換した榊は水気を拭き取り、塩で清めたら綺麗な白紙に包んでそのまま捨てるというのが一般的な処分方法とされています。
榊の交換の手間を省くには


榊の交換や水替えは、忙しい現代人にとっては意外な手間と感じてしまうこともあるかもしれません。
そんなときには、プリザーブド榊を活用してみましょう。
プリザーブド榊とは
プリザーブド榊は、本物の榊や椿の葉を特殊液に浸して作ります。
忙しい人が増えた近年では、神棚に飾る榊にプリザーブドの榊を使うことが増えています。
水やり不要で1〜2年という長期間に渡って利用できるので、交換の手間がかかりません。
高温多湿や直射日光にさえ気をつけておけば、埃を時々払う程度で十分な美しさを保つことが可能です。
プリザーブド榊のメリット
何もしなくても美しい状態をキープできるので、交換の手間を省けるのは確かなメリットといえるでしょう。神様へ捧げる感謝が変わらないのであれば、プリザーブドだからといって問題になることはありません。造花とは違い、本物の榊や椿の葉を原料にしているため神様にもためらうことなくお供えできます。
また、プリザーブド榊なら、神棚周辺を清潔に保てるメリットもあります。
普通の榊を使っていると、夏のような季節には交換できなかった榊立ての水が腐って、嫌な臭いを放ってしまうこともあります。神様は不浄を嫌うので、水の交換も難しいようなら、プリザーブド榊がおすすめです。
プリザーブド榊なら水やりそのものが不要なため、水を入れず榊立てに挿すだけで済みます。
ボタン
フジテレビフラワーネットおすすめ特集