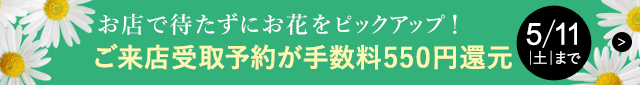
お供えのお花にバラを選んではいけない理由は?
故人の哀悼の意を込めてお供えするお花。
贈り物のお花として、バラは非常に人気の高いお花ですが、実はお墓参りなどの際にお供えする供花に、バラを選ぶのは相応しくないとされています。
当記事では、お墓参りなどの際にお供えする供花に、バラを選んではいけない理由についてご紹介します。
バラ以外でお供えに適さないお花
特に棘のあるお花と毒のあるお花は、仏事全般に向かないとされています。
上記の4つに該当するお花を、誤って供花に選んでしまわないように、ぜひ覚えていてください。
近年は「ユリは定番のお花」という印象から、供花としてお供えする方が多いのですが、匂いの強いユリの場合は避けたほうが良いです。
また特に白い墓石にされいる方は注意が必要です。
墓石についたユリの花粉は落とすことが大変難しいです。
そのため、ユリをお花にお供えするのであればきちんと花粉をとってお供えすることが必要です。お花屋さんに頼んで落としてもらうか、または自分で手袋を使用し、つまんで取っておくことをお勧めします。
基本的にはお墓にお供えする花はなんでもいいとされていますが、香りの強いものは避けた方がいいという考えもあり、しきたりやマナーに厳しい方も集まるような法要であったり、義理のご両親側や仕事関係のつながりのお墓参りの場合などは香りの強いお花は避ける方が無難です。
このように、供花にはないとされる幾つかの理由と、それに該当するお花があります。
このルールを覚えて、お墓参りなどの際には、供花として相応しいお花をお供えしてみてください。
お供えに用いるお花の選び方やマナー
お供えのお花コラム

お盆にお供えするのに最適なお花は?
お盆にはご先祖様のお墓参りに行くことが日本では1つの習わしとしてありますよね。お墓へお供えするときに使用するのに適しているお花とはどんな種類があるのでしょうか? 続きはこちらから≫

お彼岸に行く前に知っておきたいマナー
日本の伝統、お彼岸には古くから残っている常識的なマナーが存在します。親戚一同が集まるお彼岸で役に立つ、お彼岸のマナーについてご紹介いたします。 続きはこちらから≫

お供えのお花にバラを選んではいけない?その理由は?
故人の哀悼の意を込めてお供えするお花。お墓参りなどの際にお供えする供花に、バラを選んではいけない理由についてご紹介します。続きはこちらから≫

お彼岸にお供えするお花の選び方やマナーについて
日本の古くからの行事「お彼岸」。お彼岸の由来と歴史や、彼岸におすすめのお花と選び方をご紹介いたします。ぜひご参考にしてみてくださいね。続きはこちらから≫

お盆や初盆に供えるお花の選び方とは?
お盆の時期には、先祖の霊を迎えるにあたってどんなお花を準備すればいいのかは意外と知られていません。お盆に関するマナーや、おすすめのお花をご紹介いたします。続きはこちらから≫

天国のお母さんへ届ける母の日参りのおすすめなお花
天国にいる大切なお母さんへ、母の日参りにはいろいろな「想い」をのせてお花や贈り物、言葉を届けましょう。続きはこちらから≫

大切な人の命日や月命日には素敵なお悔やみのお花を
命日にどんなお花を贈ったり飾ったりすればいいのかわからないという人も多いのではないでしょうか?命日などのお悔やみに適しているお花、そしてそれに伴うマナーなども一緒にご紹介いたします。続きはこちらから≫

【ご仏壇・里帰り】天国のお母さんへ届けるお花
天国のお母さんと過ごすことのできるお盆は、まだ生きているときには言い尽くせなかった感謝の気持ちや想いを伝えることができる日です。 お母さんが好きだったお花を用意して、より一層天国のお母さんと向き合ってみましょう。続きはこちらから≫

大切な家族であるペットのお悔やみで捧げるお花
大切な家族の一員であるペット。もしその大切な家族が天国にいってしまったら… 今回は、ペットのお悔やみに関することについてご紹介します。続きはこちらから≫

今話題のプリザーブド、「榊」とは
日本最古の歴史書の古事記(こじき)にも登場し、古くから神事の際に用いられ神さまに捧げる植物の榊。 水やり不要で、いつも清潔、枯れない「プリザーブド榊」について、お手入れ方法から活用方法までご紹介します。続きはこちらから≫
フジテレビフラワーネットおすすめ特集